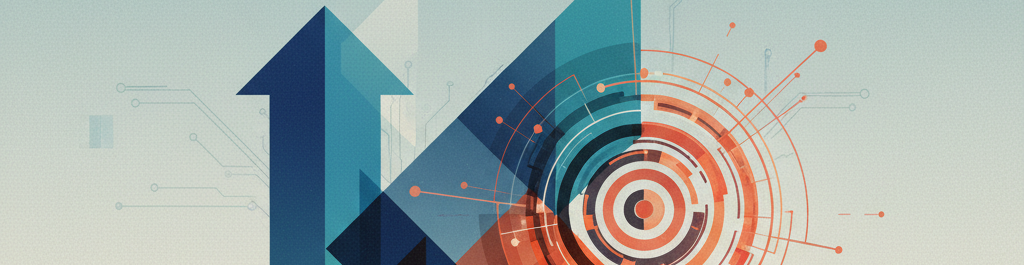これまでの連載で、マーケティングとセールスの基本的な役割と、両者が連携する構造を定義した。しかし、これらの機能を効果的に実行するためには、場当たり的な活動の積み重ねではなく、一貫した論理に基づく「戦略」が不可欠である。
では、その戦略はどのようにして構築されるのか。本稿では、あらゆるマーケティング活動の土台となる戦略の「設計図」として、二つの重要なフレームワークである「STP分析」と「4E理論」を解説する。
戦略の起点:誰に、どのような価値を届けるか(STP分析)
マーケティング戦略の出発点は、「全ての顧客を満足させることはできない」という事実を認識することにある。限られた経営資源を最も効果的に投下するためには、市場を精査し、自社が最も価値を提供できる顧客層を見定め、その顧客に対して独自のポジションを築く必要がある。この一連の思考プロセスを体系化したものがSTP分析である。
1. セグメンテーション(Segmentation:市場の細分化)
まず、多様なニーズが混在する巨大な市場を、ある共通の軸に基づいて意味のある小さな集団(セグメント)に分割する。この軸には、年齢や性別といった人口動態変数、ライフスタイルや価値観といった心理的変数、あるいは製品の使用頻度や求める便益といった行動変数などが用いられる。ここでの目的は、市場の構造を客観的に理解することにある。
2. ターゲティング(Targeting:狙うべき市場の決定)
次に、細分化されたセグメントの中から、自社の強みやビジョンと照らし合わせ、最も魅力的で、かつ競争優位性を発揮できるセグメントを選び出す。全てのセグメントを追うことは、戦力の分散を意味し、結果として誰にも響かないメッセージを発信することにつながる。ターゲティングとは、戦うべき場所を選択するという、戦略の核をなす意思決定である。
3. ポジショニング(Positioning:独自の立ち位置の確立)
最後に、ターゲットとして定めたセグメントの顧客の頭の中に、競合製品と比較して自社製品が持つ独自の価値を、明確かつ魅力的に位置付ける。例えば、「高品質だが高価格」「機能は限定的だが圧倒的に安い」「特定の用途に特化した専門品」といったように、顧客が製品を選択する際の判断基準となる独自の座標軸を設定し、その中で唯一無二の存在として認識されることを目指す。
このSTP分析によって、「どの市場で、誰に対して、どのような存在として認識されるか」という、マーケティング活動全体の方向性が定められる。
戦略の実行:顧客視点へのパラダイムシフト(4Pから4Eへ)
STPによって戦略の骨格が定まったら、次はその戦略を具体的な戦術に落とし込む必要がある。その際に伝統的に用いられてきたのが、4P理論というフレームワークである。
- Product(製品):どのような製品やサービスを提供するか。
- Price(価格):それをいくらで提供するか。
- Place(流通):どこで、どのようにして提供するか。
- Promotion(販促):どのようにしてその存在を知らせるか。
この4Pは、企業側(売り手)の視点からマーケティング要素を整理した、非常に強力なフレームワークである。しかし、顧客が主導権を握る現代の市場においては、この視点を顧客側(買い手)の視点へと転換させる必要性が指摘されている。そこで登場したのが、4E理論である。
| 売り手視点(4P) | 買い手視点(4E) | 説明 |
|---|---|---|
| Product (製品) | Experience (顧客体験) | 顧客は単なる「モノ」ではなく、購入から使用、サポートに至るまでの全ての「体験」を評価する。 |
| Price (価格) | Exchange (交換価値) | 顧客は金銭だけでなく、時間や情報も提供する。その全てに見合う「価値の交換」が成立しているか。 |
| Place (流通) | Everyplace (あらゆる場所) | 顧客は店舗やウェブサイトといった物理的な「場所」に縛られず、あらゆる接点でブランドと繋がることを期待する。 |
| Promotion (販促) | Evangelism (熱狂と推奨) | 企業からの一方的な宣伝ではなく、優れた体験を通じて顧客自身が熱狂的な推奨者(伝道者)となる。 |
この4Pから4Eへの視点の転換は、単なる言葉遊びではない。それは、企業中心の論理から顧客中心の論理へと、マーケティングの根本的なパラダイムシフトを要求するものである。STPで定めた戦略的ポジションを、4Eの観点から具体的な戦術として設計することで、初めて現代の顧客に響くマーケティングが実現される。
戦う場所、立ち位置、そして戦い方
マーケティング戦略とは、STP分析によって「戦う場所」と「立ち位置」を定め、4E理論という顧客中心の視点から具体的な「戦い方」を設計する、一連の論理的なプロセスである。この設計図を持つことで、日々の活動は一貫性を持ち、その効果を最大化することが可能となる。
この戦略的基盤の上に、現代のテクノロジーや社会情勢を反映した、より具体的な理論が存在する。次回は、その中でも特に重要な「マーケティング5.0」と「パーパス・ドリブン戦略」について掘り下げる。